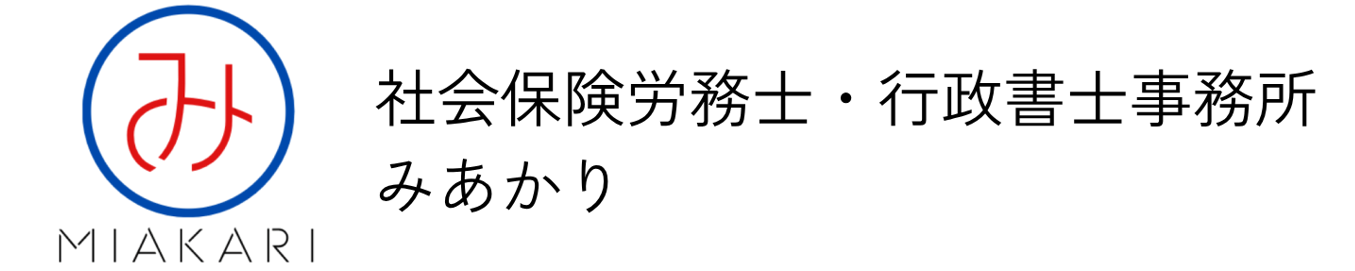①『就業規則・各種規程作成、改定』
②『在留資格手続き(外国人雇用サポート)』
③『社労士診断認証制度』
④『会社設立サポート(労務ワンストップサービス)』
業務の詳細な説明です。
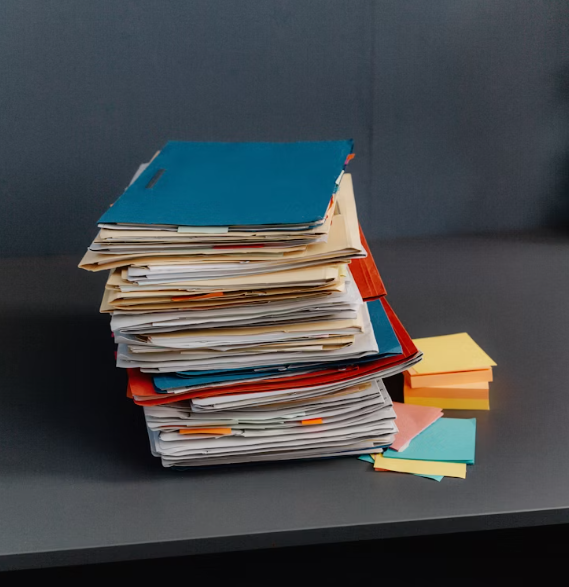
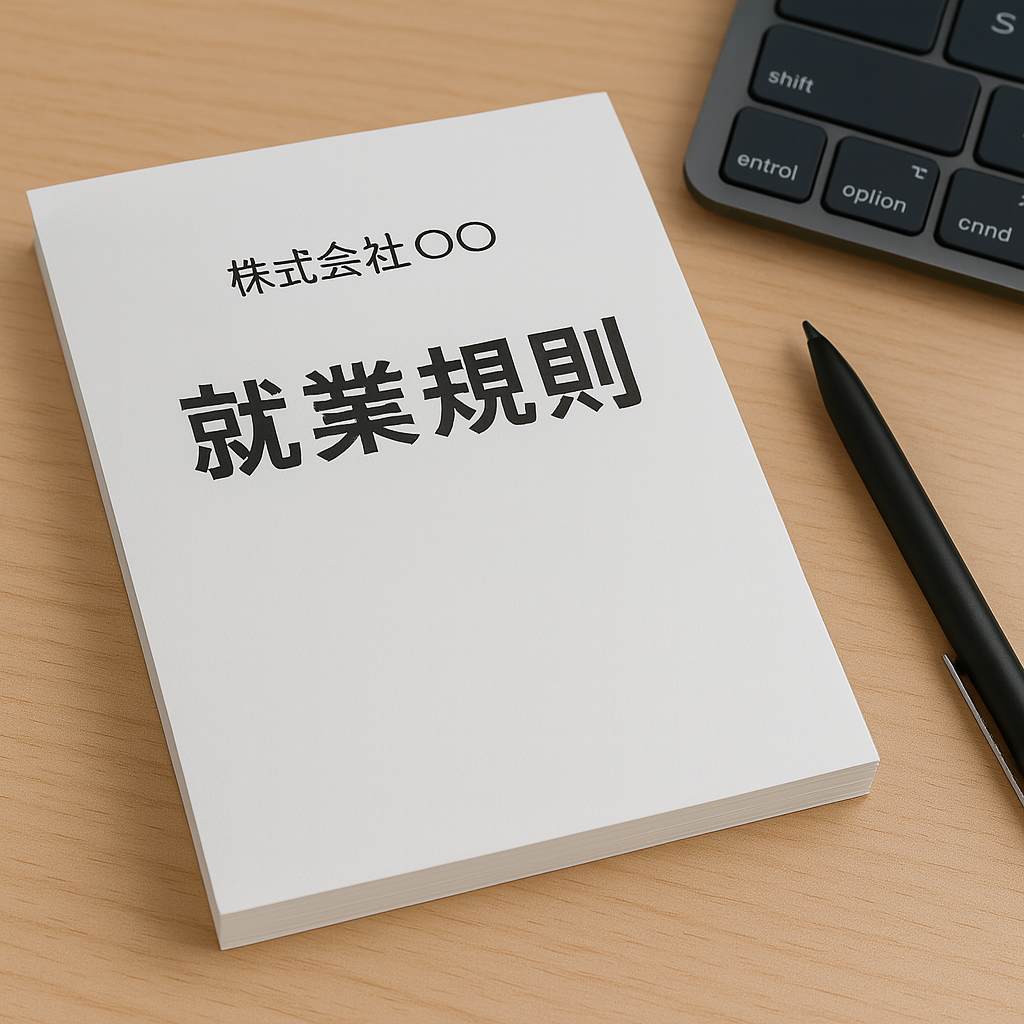



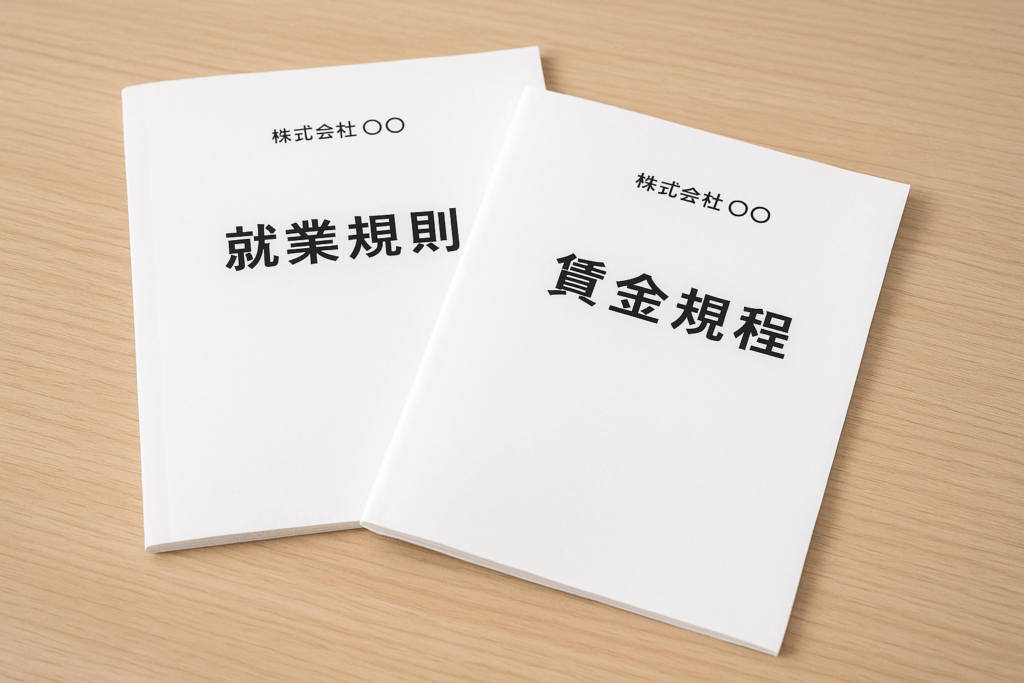

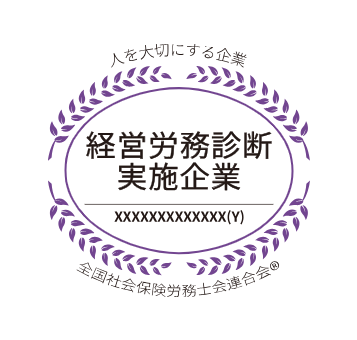
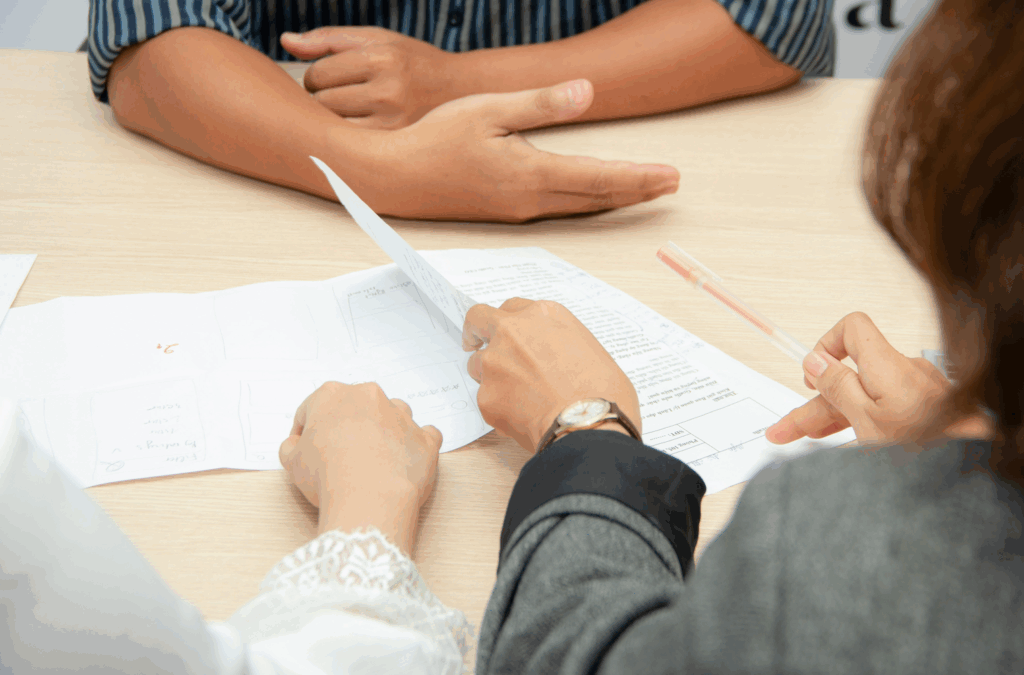


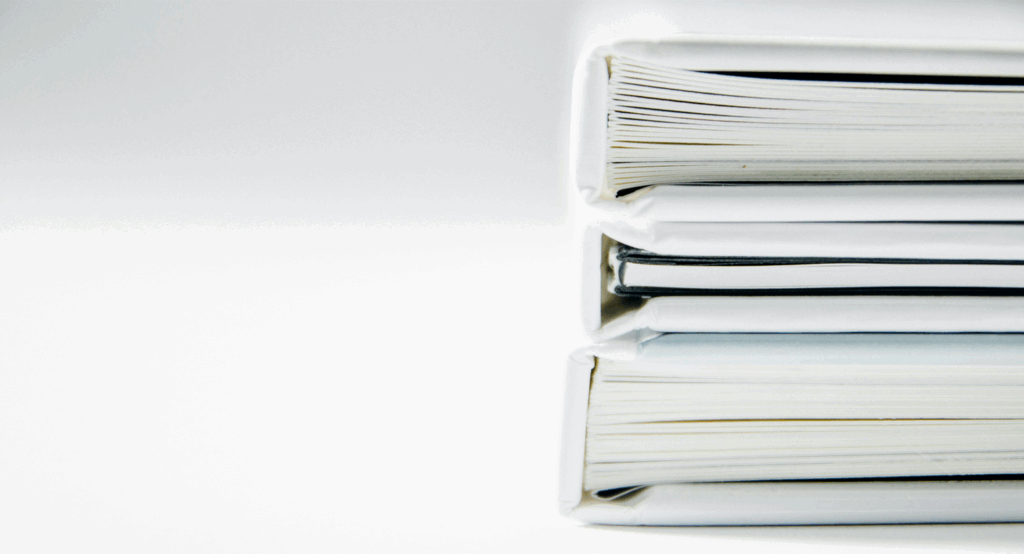
①就業規則・各種規程作成、改定
~はじめに~
『就業規則』とは、労働者の賃金や労働時間等の労働条件に関すること、職場内の規律等について定めた職場における規則集です。
つまり、就業規則の規定事項は、『労働者の労働条件や職場のルール』となります。
なお、常時10人以上の労働者を使用している事業場では、就業規則を作成し、過半数労働組合または労働者の過半数代表者からの意見書を添付し、『所轄労働基準監督署に届け出る』必要があります。
= 常時10人以上の労働者を雇うこととなれば、就業規則の作成、届出の義務が発生します。
※常時10人未満の労働者を雇う場合でも、労働条件、職場のルールの整備のため、就業規則の作成は望ましいと言えます。
Q:わざわざ作成を依頼する必要があるのか。厚生労働省のモデル就業規則や市販の就業規則を流用すれば良いのではないか?
A:会社によって、労働者の労働条件や職場のルールは異なります。
そのため、厚生労働省のモデル就業規則や市販の就業規則を安易に流用することにより、実態とは異なる権利義務を発生させる恐れがあります。
休職制度、特別休暇、福利厚生等、法令上の定めのない事項をどのように定めるのか、雇用形態(正社員とパートタイマー等)によってどのような労働条件を定めるのか(別規程を作成するのか)等、就業規則は、会社の実情を踏まえた上での作成が重要となります。
Q:賃金規程、育児介護休業規程等、何の規程を作れば良いのかわからない。
A:労働条件、職場内の規律等を定める就業規則に関して、委任規定を設けた上で、詳細を別規程に定めるケースもあります。
賃金、育児介護休業等に係る事項を就業規則に明記することは、確かに複雑化、煩雑化を招く面があります。そのため、やはり賃金、育児介護休業に関する事項に関しては、別規程を設けるケースも多いです。
当事務所にご依頼いただいた場合、『何の規程を作成しなければならないのか』という点に関しても検討いたします。
Q:就業規則の他、策定が義務付けられている規程があると聞いた。
A:策定が義務付けられている規程は存在します。
例えば、個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)において、原則として従業員の数が100人以上の事業主は、個人データの取扱いに係る規律の整備をしなければならない旨が示されています。
また、特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)では、原則として従業員の数が100人以上の事業主は、特定個人情報等の適正な取扱いを確保するために取扱規程等を策定しなければならない旨が示されています。
個人データや特定個人情報等に関する事項を就業規則に明記することはやはり複雑化を招くため現実的ではなく、通常、別規程を設けることとなります。(例:個人情報保護管理規程、特定個人情報等保護管理規程)
各種規程の作成に関して、ご不明な点があればお気軽にご相談ください。
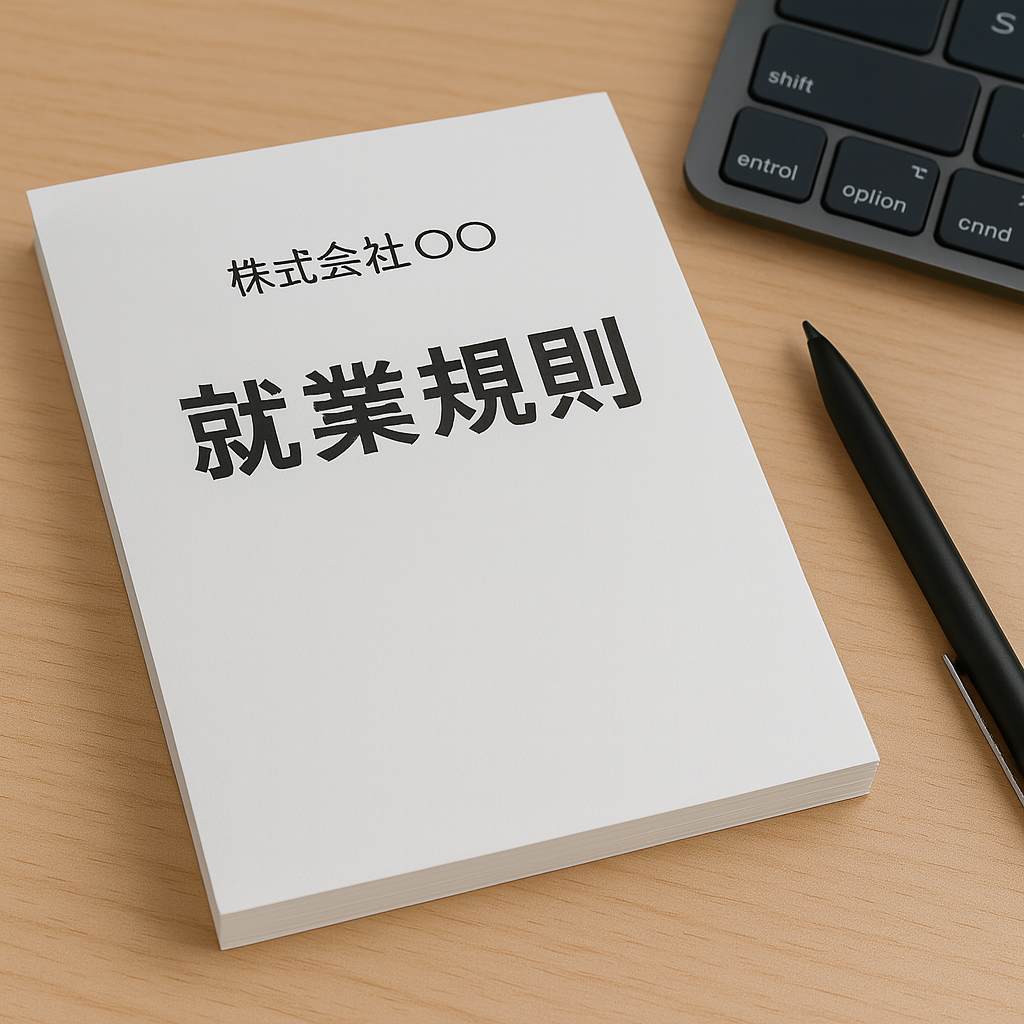
②在留資格手続き(外国人雇用サポート)
~はじめに~
我が国の外国人に関する入国、在留に関する事項は、基本的に出入国管理及び難民認定法(入管法)の定めるところによります。
外国人は、『在留資格』をもとに日本に中長期滞在することとなります。
在留資格とは、日本で行うことが出来る活動や、日本において有する身分・地位を類型化したもので、世間一般的には『ビザ』と呼ばれています。
ただし、ビザ(査証)と在留資格は厳密には別のものであるため注意が必要です。
(当事務所HPでは、便宜上、在留資格(ビザ)と表記させていただいております。ご了承ください。)
たしかに、在留資格(ビザ)は外国人本人に関するものです。
しかし、外国人を雇う事業主という観点から考えると、「不法就労助長罪」や「外国人雇用状況の届出」といった事業主も知らなかったでは済まされない法的事項が存在します。
= 外国人の労働者を雇うこととなれば、事業主として知っておかなければならないこと、注意しなければならない事項が存在します。
Q:他の事務所の在留資格手続きと何が違うのか?
A:特徴は二点あります。
第一に、当事務所は、行政書士、社会保険労務士のダブルライセンス、入管法と労働法に係る実務の経験を活かし、就労系の在留資格に特化した手続きを行っている点です。
入管手続きは、行政書士の業務独占ですが、就労系の在留資格は、業務内容や労務管理体制の適正さ等も重要となります。そのため、本来、労働法の専門的な知見がなければ正しいリスクチェックや改善案の提示はできません。
また、外国人の雇い入れ事前のチェックの仕組みも設けているのも特徴です。
私(代表 河村)は、以前行政書士として外国人の在留資格に関する書類作成手続きに従事していましたが、これは事前に対策を講じていれば在留資格の手続きをスムーズに行うことができたはずと思うことが何度もありました。
例えば、雇用契約書上、技術・人文・知識の在留資格では従事することができない業務が記載されていたケースや会社の安定性に欠ける時期に申請せざるを得ないケース等がありました。
入管での在留資格手続きに関する不許可リスクを避けるためには、雇用契約書・労働条件関係、就業規則、賃金・社会保険関係、業務内容等、会社に関する事前の労務監査が望ましいのではないかと私は強く考えています。
この事前監査から在留資格手続きまでのワンストップ業務を手掛けているケースは、ほぼないと思いますが、不許可リスクを避けるこの仕組みも当事務所の大きな特徴であると自負しております。
Q:誰が依頼をすれば良いのか?
A:外国人本人ではなく、雇い入れる会社、勤務先の会社のご担当者から依頼いただきたいと思っています。
上記の事前監査の仕組みもそうですが、私は「外国人本人が行政書士を探してビザの手続きを依頼する」という仕組みにも疑問を抱いております。
在留資格の手続きは、勿論外国人本人にとって、本邦に在留するために非常に重要であり、明暗を分ける重大な手続きです。
ただ、その外国人が勤務する、勤めている会社にとっても、最悪の場合は従業員が一人いなくなるという重大な手続きであることに変わりはありません。
在留資格申請は「外国人本人」が申請人であるという制度面の背景、本人依頼を受けやすい行政書士の営業構造上の事情等により、これまで、外国人本人が行政書士を探してビザの手続きを依頼するという仕組みが確立されてきました。
しかし、外国人雇用状況届出制度や技能実習・特定技能制度等、企業の体制整備が在留資格の審査に直結する面もあります。
また、雇用主としてのコンプライアンス対応としても従業員の在留資格に関する手続きは、会社が主体的に関与した方が良いと私は考えます。
従業員の社会保険や雇用保険の手続きですら会社が代行するのに、不許可リスクのある在留資格に関する手続きに会社が関与しないのは、実は非常に不自然なことだと思います。
Q:外国人雇用、在留資格(ビザ)に関して、社内研修を行ってほしい。
A:当事務所では、外国人雇用・労務管理基礎研修(セミナー)を実施しております。
原則として、報酬額は、35,000円(税別/2時間)です(顧問先の場合:30,000円(税別/2時間 )です)。
※東京都以外へのご訪問による実施をご希望の場合、別途交通費(実費)を請求させていただきます。ご了承ください。

③社労士診断認証
※引用:全国社会保険労務士会連合会「社労士診断認証制度」説明動画
~はじめに~
全国社会保険労務士会連合会では労務コンプライアンスや働き方改革に取組む企業を支援するため、社労士が企業を診断し、認証マークを発行する事業を進めています。
診断診断マークの取得により、企業の人事労務管理体制の改善や強化のみならず、認証マークのHP・リクルートサイト掲載により企業PR・採用等に役立てることもできます。
認証マークは、段階に応じて三種類存在します。
自社の状況に応じて、適宜、人事労務管理体制の改善・強化に努めながら、認証のステップアップを目指すこととなります。
【認証マークの詳細】
(1)職場環境改善宣言企業

職場環境の改善に取り組むための「職場改善宣言企業」確認シートの項目を確認のうえ、企業自らが職場環境の改善を宣言することとなります。
全国社会保険労務士会連合会より確認・認証手続き後、 マークが付与され、認証企業として全国社会保険労務士会連合会の企業情報サイトに掲載されます。
(2)経営労務診断実施企業
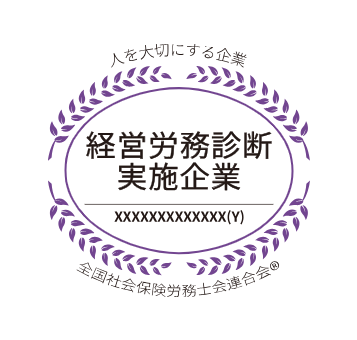
「職場環境改善宣言」を行なった上で、「経営労務診断基準」にもとづき所定の項目について確認を受けた企業に全国社会保険労務士会連合会よりマークが付与され、全国社会保険労務士会連合会の企業情報サイトにマーク情報が掲載されます。
(3)経営労務診断適合企業

「職場環境改善宣言」を行なった上で、所定の項目について社労士の確認を受け、「経営労務診断基準」にもとづき必須項目のすべてが適正と認められた企業に、全国社会保険労務士会連合会よりマークが付与され、全国社会保険労務士会連合会の企業情報サイトにマーク情報と各項目の調査結果が掲載されます。
※社労士認証制度のメリット
【ガバナンス強化、コンプライアンス対応】
昨今では、ガバナンス強化やコンプライアンス対応が企業の一つの課題となりつつあります。
社労士認証制度によって、人事労務領域に関する問題点の把握や整理ができ、また内外に対するコンプライアンス対応の証明にもなります。
【職場環境改善、働きやすい職場作りへのきっかけ】
職場環境の整備や働きやすい職場作りも昨今の人事労務領域のテーマです。
社労士認証制度を通じて、顕在化した人事労務領域に関する問題点の解決、解消を通じて、職場環境改善、働きやすい職場作りに繋がります。
【採用活動におけるPR、企業の信頼性の向上】
認証マークのHP・リクルートサイト掲載、全国社会保険労務士会連合会の企業情報サイトへの掲載により、対外的に人事労務領域の適切な管理、整備された職場環境であることをアピールできます。
超高度情報化社会において、「認証マーク」は、求職者や顧客にとっての信頼性の向上に繋がる面があります。
※下記の全国社会保険労務士会連合会の社労士認証制度のページもぜひご確認ください。
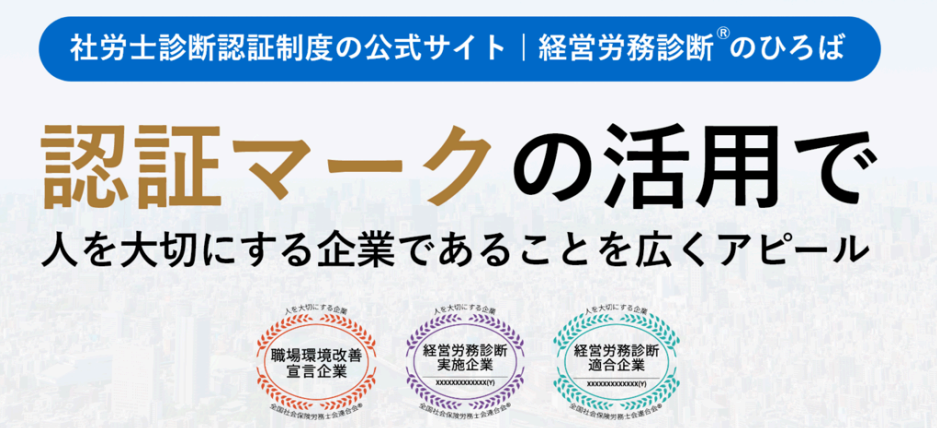
④会社設立サポート(労務ワンストップサービス)
~はじめに~
会社設立とは、新しく法人をつくり、事業を行うための組織を法律的に成立させる手続きです。
個人事業と異なり、法人格を持つことで信用力が高まり、契約や資金調達の場面で有利になります。
会社の形態には株式会社、合同会社、合名会社、合資会社等があります。
ただし、実際に多く設立されているのは株式会社と合同会社であり、他の形態はまれです。
株式会社の場合は、定款を作成し、公証役場で認証を受けたうえで、法務局に登記申請を行います。
合同会社の場合は、公証役場での認証は不要ですが、登記申請は必要です。
登記が完了すると、会社は正式に法人として認められ、事業活動を開始できるようになります。
会社設立は、将来の経営の枠組みを定める重要なステップです。
Q:株式会社と合同会社の違いは?
A:株式会社とは、最も一般的な会社形態で、設立件数の大半を占めます。
出資者(株主)は出資額を限度として責任を負う「有限責任」となり、対外的な信用度も高いのが特徴です。将来的に規模を拡大したい方、融資や投資を受けて事業を成長させたい方に向いています。
そして合同会社とは、2006年に新設された比較的新しい会社形態で、株式会社に比べて設立費用が安く、手続きも簡易です。
出資者全員が有限責任であり、内部のルールを柔軟に決められるため、少人数での事業やコストを抑えたい方に適しています。近年は外資系企業やスタートアップでも利用されることが増えています。
その他、合名会社、合資会社もありますが、実務的には 株式会社か合同会社のいずれかを選ぶのが一般的です。
当事務所では、お客様の事業計画や目的に応じて最適な会社形態をご提案いたします。
Q:他の事務所の会社設立手続きと何が違うのか?
A:多くの事務所では、会社設立の登記や定款認証等「法人設立の入口部分」のみに対応しています。しかし、実際には設立直後から社会保険・労働保険の新規適用届の手続きや社内ルールの制定が必要となり、労務の整備が会社経営の土台となります。
当事務所では、行政書士としての会社設立手続きに加え、社会保険労務士としての労務関連手続きをワンストップでご提供しています。
「会社設立労務ワンストップスタンダードプラン」では、会社設立と同時に社会保険・労働保険の手続きをまとめて対応し、さらに「プレミアムプラン」では、設立に加えて雇用契約書や就業規則一式の作成までセットでご提供いたします。
これにより、設立直後から労務リスクを回避し、安心して人を雇える体制を整えることができます。
他の事務所では分業になりがちな「設立+労務整備」をまとめてサポートできる点が大きな違いです。
単なる会社設立手続きにとどまらず、将来を見据えた労務環境の整備まで一貫して伴走するのが当事務所の強みです。
Qどこまで対応可能か?
A:当事務所では、行政書士として会社設立に必要な定款作成・認証手続きや関連書類の作成をサポートいたします。
さらに社会保険労務士として、社会保険・労働保険の新規適用届や従業員の資格取得手続き、また雇用契約書案や就業規則一式の作成まで一括で対応可能です。
ただ、登記申請については司法書士の独占業務となるため、必要に応じて司法書士をご紹介いたします。
また、設立後の税務手続きや会計顧問をお探しの場合には、税理士をご紹介することも可能です。
会社設立から労務・税務・登記までワンストップでスムーズにつなげる体制を整えています。
必要な専門家との連携を含めて一貫してご案内できるのが特徴です。
「どこに何を頼めばよいのか分からない」という不安を解消し、安心して設立準備を進めていただけます。